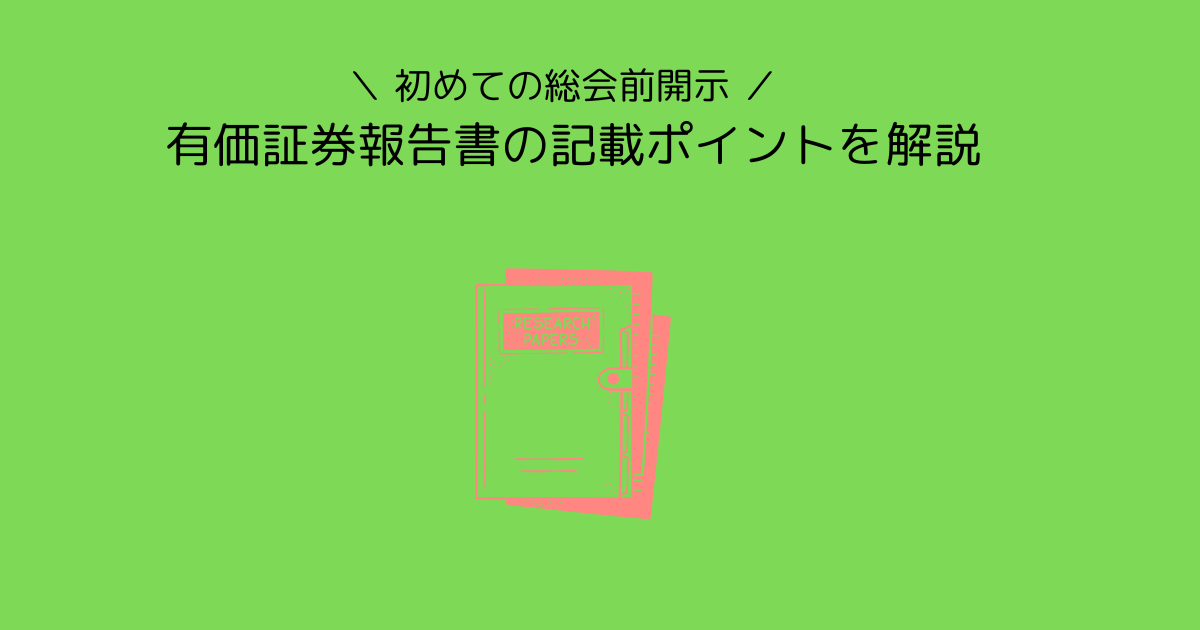近年、株主や投資家への情報開示の迅速化が求められる中、有価証券報告書(有報)を定時株主総会前に提出する企業が増えています。しかし、従来の「株主総会後に提出」する形式から切り替えるにあたっては、報告書の記載内容やその表現方法にいくつかの重要な注意点があります。本記事では、2025年3月に公表された最新ガイドラインをもとに、企業が気をつけるべきポイントを解説します。
◆ 前提:株主総会前に提出するとは?
通常、有報は株主総会の終了後に提出されますが、これを株主総会前に提出する場合には、「予定されている決議事項」について、その旨と概要を記載することが求められます。これは、内閣府令(企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式 記載上の注意(1)g)に基づいています。
◆ 主な留意点:どこをどう書くべきか?
1. 配当関係
- 主要な経営指標等の推移
1株当たり配当額が確定していない場合でも、予定額を記載し「定時株主総会で決議予定」である旨を明示。 - 配当政策
業績見通しや株主還元方針に基づいて、予定配当額や今後の方針を具体的に記載。 - 配当に関する注記事項(株主資本等変動計算書)
「配当の効力発生日が翌事業年度となる予定」など、将来的な議案としての位置づけを記載。
2. ガバナンス関連
- コーポレート・ガバナンスの概要
予定されている取締役会の構成や機関設計に変更がある場合、その予定内容を具体的に記載。 - 役員の状況
株主総会で選任予定の役員について、予定構成・女性比率などの数値情報も含めて明示。 - 監査の状況
監査体制に変更がある場合は、変更後の構成や背景も記載。 - 役員報酬等
株主総会で決議予定の報酬制度(特に譲渡制限付株式など)については、その目的や枠組みを含めて概要を記載。
◆ 記載が難しいケースでは?
提出時点で詳細な情報が未確定の場合、「可能な範囲」で記載すれば足ります。また、株主総会で議案が否決された場合には、臨時報告書の提出によって対応することが認められており、有報の訂正までは必要とされません。
◆ 報告書に添付する計算書類等は?
会社法に基づく計算書類や事業報告については、「株主総会に報告・承認予定」である内容をそのまま添付して差し支えありません。
◆ 実務への影響と対応例
上場企業の中には、すでにこの方式を採用している事例も増えてきています。信越化学工業や日本ライフライン、三菱総合研究所などでは、予定事項を明確に注記する形で有報を株主総会前に提出しています。
◆ まとめ
株主総会前に有報を提出する場合、「予定であることの明示」と「概要の記載」がポイントです。過去の報告様式とは異なる記載が必要になるため、初めて対応する企業はガイドラインや他社事例を参考に、事前準備を入念に行いましょう。
参考:企業内容等の開示に関する内閣府令、金融庁ガイドライン(2025年3月公表)