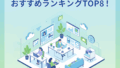いよいよ来期から、日本でも新しいリース会計基準が本格的に適用されますね。
「うちの会社は大丈夫?」と、少し不安に感じている経理担当者の方も多いのではないでしょうか。
実は、この新基準のモデルとなったIFRS第16号は、海外ですでに数年前から適用されています。そして、多くの企業が同じような課題に直面し、数々の試行錯誤を繰り返してきました。
この記事では、IFRS適用時の先行事例を基に、日本の経理担当者がこれから直面するであろう**「5つの重要な論点」**と、その対策を具体的にお伝えします。
そもそも何が大きく変わるのか?
新リース会計基準の最大の変更点は、これまでオフバランス(貸借対照表に載らない)だったオペレーティング・リースが原則としてすべてオンバランスされることです。 つまり、単純な賃貸借契約だと思っていたものまで、「使用権資産」と「リース負債」として貸借対照表に計上しなければならなくなります。 これにより、企業の財務諸表の見え方は大きく変わります。IFRS適用時には、この変更が予想以上に大きな影響を及ぼしました。
IFRS先行事例に学ぶ、新リース会計でつまずく論点TOP5
すべての契約書を洗い出せ!「リースの定義」の罠
IFRS適用時に最も時間と労力がかかったのが、そもそも「何がリースに該当するのか」を特定する作業でした。新基準では、契約の実態が「識別された資産の支配を、一定期間にわたり対価と交換に移転する」ものであれば、それはリースと判断されます。これにより、これまで費用処理していたITサーバーのレンタル契約や、特定の車両を使った輸送サービス契約などもリースに該当するケースが出てきました。
経理部門だけでなく、法務、総務、IT、購買など、契約に関わる全部門を巻き込み、社内に存在するすべての契約書をリストアップするプロジェクトを今すぐ始めましょう。「リース」という名前がついていない契約にこそ、隠れたリースが潜んでいます。
判断の連続!「リース期間」と「割引率」の見積もり
リース負債と使用権資産の金額は、リース料総額の現在価値で計算しますが、その計算要素である「リース期間」と「割引率」の決定には高度な見積もりと判断が求められます。特に、契約更新オプションを行使するかどうか、リースに固有の利率が分からない場合の「追加借入利子率」をどう算定するかで、担当者は頭を悩ませました。
自社のリース契約に更新オプションや解約オプションが含まれていないかを確認し、行使可能性についての方針を事前に固めておきましょう。また、追加借入利子率については、財務部門と連携し、自社の信用力やリース期間に応じた利率をどのように算定するか、監査法人とも事前に協議しておくことが重要です。
救済措置を使いこなせ!「短期・少額リース」の重要性
新基準では、例外的にオンバランスしなくてよい「免除規定」が設けられています。それが「短期リース(12ヶ月以内)」と「少額リース(新品価額が少額な資産)」です。IFRS適用当初、この規定を十分に理解・活用せず、PC1台、コピー機1台まで資産計上しようとして、実務がパンク状態に陥る企業が散見されました。
自社として「少額リース」の金額基準(例えば、新品価額50万円以下など)を明確に設定し、会計方針として文書化しましょう。どのリースが免除規定に該当するかを事前に整理しておくだけで、適用初年度の業務負担を大幅に軽減できます。
経営層に説明できますか?財務指標(KPI)への大きな影響
リースがオンバランスされると、総資産と負債が同時に増加します。これにより、自己資本比率やROA(総資産利益率)は悪化する一方、支払リース料が減価償却費と支払利息に変わるため、EBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益)は見かけ上、良く見えます。このメカニズムを経営層や投資家にきちんと説明できず、混乱を招くケースがありました。
新基準を適用した場合の財務諸表への影響額を早期に試算し、主要な経営指標(KPI)がどのように変動するのかをシミュレーションしましょう。その結果を基に、経営層や関連部署への説明資料を準備しておくことが不可欠です。
経理だけの問題じゃない!業務プロセスとシステム対応
リース情報の収集・管理、複雑な計算、そして仕訳の計上まで、新基準の要求はExcelでの手作業管理には限界があります。多くの企業が、リース管理システムの導入や、既存の会計システムの改修に迫られましたが、準備が遅れたために適用開始時に大きな混乱をきたしました。
自社のリース契約の件数を把握し、Excel管理で対応可能か、システム導入が必要かを早期に判断しましょう。システムを導入する場合は、選定から導入、テストまで半年以上かかることもあります。情報システム部門と連携し、すぐに検討を開始すべきです。
まとめ:新リース会計基準は、準備が9割
今すぐ始めるべきこと
- プロジェクトチームの発足
経理だけでなく、関連部署を巻き込んだ横断的なチームを作りましょう。 - 契約の網羅的な洗い出し
社内のすべての契約をリストアップし、リースに該当するかを検討しましょう。 - 会計方針の決定
少額リースの基準値など、判断が必要な項目の方針を決め、監査法人と協議しましょう。 - システム対応の検討
Excelか、専用システムか。自社の規模に合った管理方法を決めましょう。
新リース会計基準への対応は、まさに「準備が9割」です。海外の事例を参考に、早期に準備を進めることで、スムーズ