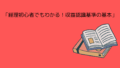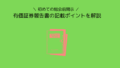投資先を選定する際、企業の収益性を示す指標として「営業利益率」は非常に重要です。営業利益率は、企業の本業による利益の割合を示し、以下の計算式で求められます。
営業利益率(%) = (営業利益 ÷ 売上高) × 100営業利益率が高いほど、本業での収益性が高いと評価されます。
業種別営業利益率の目安(2024年データ)
以下の表は、主要業種の営業利益率の平均値を示しています。業種によって利益率は異なるため、同業他社と比較することが重要です。
| 業種 | 営業利益率(%) |
|---|---|
| 不動産業・物品賃貸業 | 11.25 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 6.90 |
| 情報通信業 | 5.45 |
| 建設業 | 3.85 |
| 製造業 | 3.79 |
| サービス業 | 3.25 |
| 小売業 | 1.34 |
| 卸売業 | 2.11 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | -3.85 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 0.61 |
| 運輸業・郵便業 | 0.72 |
出典: だいぞうコンサルティング(dyzo.consulting)
業種別の営業利益率から見る収益性の傾向
上記の表は、主要な業種ごとの平均的な営業利益率を示したものです。業界ごとにビジネスモデルやコスト構造が異なるため、利益率にも大きな差が見られます。
たとえば、「不動産業・物品賃貸業」は営業利益率が**11.25%**と非常に高く、これは安定した賃貸収入や物件売却益が本業の利益に直結しやすいビジネスモデルによるものです。
一方、「小売業(1.34%)」や「卸売業(2.11%)」のような業種は、薄利多売が基本となるため、どうしても利益率は低くなりがちです。
特に注意が必要なのは「宿泊業・飲食サービス業」で、平均営業利益率が**マイナス(-3.85%)**となっており、これは人件費・原材料費の高騰やコロナ禍の影響が長引いたことも一因です。
逆に、「情報通信業(5.45%)」や「専門・技術サービス業(6.90%)」などの分野は、人材や知識を活かした高付加価値型のビジネスが中心となるため、営業利益率が比較的高い傾向にあります。
投資判断では「業種ごとの差」を意識
営業利益率を見るときは、「数値が高いか低いか」だけでなく、業種特有の水準との比較が大切です。
たとえば、情報通信業の企業で営業利益率が10%であれば高評価ですが、小売業で同じ10%なら「非常に優秀」と評価されるべきです。
このように、業種別の特性を理解することで、より正確な投資判断が可能になります。
実際の上場企業の営業利益率例
具体的な企業の営業利益率を知ることで、業界内での位置付けや投資判断の参考になります。以下は、営業利益率が高い上場企業の例です。
| 企業名 | 証券コード | 業種 | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|
| 全国保証株式会社 | 7164 | 金融業 | 78.27 |
| 手間いらず株式会社 | 2477 | インターネット広告 | 70.48 |
| 株式会社アサックス | 8772 | 金融業 | 69.53 |
| 宮越ホールディングス | 6620 | 不動産業 | 65.35 |
| ペプチドリーム株式会社 | 4587 | バイオ | 59.87 |
| 日本取引所グループ | 8697 | 金融業 | 55.41 |
| 株式会社オービック | 4684 | システム開発 | 53.72 |
| 株式会社ランド | 8918 | 不動産業 | 53.23 |
| 株式会社ファーストロジック | 6037 | サービス業 | 51.89 |
| 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 50.31 |
出典: ノウハウTIPS(know-how.fun)
営業利益率を活用した投資判断のポイント
- 業種特性を理解する: 同業他社と比較して営業利益率が高いか低いかを確認しましょう。
- 安定性を評価する: 営業利益率が安定して高い企業は、競争優位性が高いと考えられます。
- 過度なコストカットに注意する: 営業利益率が高すぎる場合、品質低下や過度なコスト削減が行われていないか確認しましょう。
まとめ
営業利益率は、企業の本業による収益性を測るうえで非常に重要な指標です。
- 業種によって平均的な営業利益率は大きく異なるため、同業他社との比較がカギとなります。
- 単に「高い・低い」で判断するのではなく、安定性や企業の成長戦略とあわせて分析することで、より正確な投資判断が可能になります。
- 営業利益率が安定して高い企業は、競争力やブランド力が強く、将来的にも継続的な利益が期待できる傾向があります。
株式投資では、PERやROEといった他の指標と組み合わせながら、営業利益率を通じて「その企業の本当の稼ぐ力」を見極めていきましょう。